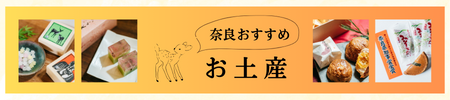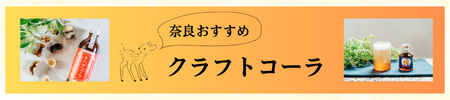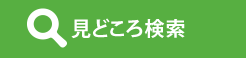
![]()
正倉院展
掲載日:2025年9月17日
華麗にして精緻な天平工芸の極み
「第77回 正倉院展」
10月になれば、いよいよ「正倉院展」シーズンの到来。ご注意いただく内容をまとめましたので、お出かけの前にご確認ください。
令和7年(2025)の「正倉院展」について
2025年10月25日(土)から11月10日(月)までの17日間にわたり開催される、第77回目となる正倉院展。調度品、楽器、服飾品、仏具、文書といった正倉院宝物の全容をうかがえるような多彩なラインナップの品々が出陳されます。観覧には、事前予約制の日時指定券(当日各時間枠開始時刻まで販売)が必要です。
世界に誇る「正倉院宝物」
シルクロードの終着点ともいわれる奈良。奈良時代にはすでに国際交流が盛んで、異国の文化や文物が遣唐使などによってたくさんもたらされました。その刺激を受けて高級素材を用い、技の限りをつくした異国情緒あふれる工芸品、調度品、仏具、楽器などが国内でも作られました。正倉院にはこれらのほか、戸籍などの文書類、経典、薬物など、膨大な点数の品々が収められ、整理された宝物だけでも9千件を超えています。
この宝物のはじまりとなったのは、天平勝宝8歳(てんぴょうしょうほうはっさい)(756)の聖武天皇の七七忌に、光明皇后が天皇の冥福を祈って大仏に献上した天皇ゆかりの品々です。その後、時を経て、宝庫は3つに仕切られ、北倉にはおもに聖武天皇のご愛用品、中倉には東大寺に献納された品々や文書、南倉には仏具や大仏開眼会(だいぶつかいげんえ)などの東大寺の儀式に関わる品々が納められました。1200年もの昔から大切に継承された宝物群は世界にも類がなく、まさに世界の至宝ともいえるのです。
そもそも正倉院って?
学校できっと一度は習う「正倉院」を、実際にご覧になったことはありますか? 正倉院は東大寺大仏殿の北西、約300mのところにあり、現在は宮内庁の機関である正倉院事務所が管理しています。国宝に指定されている「正倉院正倉」は南北約33m、高さ約14m、総ヒノキの高床式校倉造(あぜくらづくり)の倉庫で、8世紀中頃に建てられました。かつては「校倉造の木材が呼吸して通気性がよかったために宝物が守られた」という説が信じられていましたが、実際には、宝物は辛櫃(からびつ)と呼ばれる櫃に収められたために適度な温湿度調整がなされ、今に伝わったというのが正しいようです。現在宝物は、正倉に近い鉄筋コンクリートの東宝庫・西宝庫で管理されており、正倉には櫃などが納められています。正倉院宝物は通常非公開ですが、毎年10月から11月にかけて総点検が行われ、この時に宝物の一部が奈良国立博物館に貸し出されて、「正倉院展」として公開されます。
正倉院は1つだけじゃなかった?
現在の「正倉院」の本当の名前は「正倉院正倉」といいます。奈良~平安時代、日本各地の役所や大きなお寺には、大事なものを収める「正倉」と呼ばれる倉庫が置かれ、正倉がたくさん建ち並ぶ一画を「正倉院」と呼びました。つまり正倉院は、かつては一般名詞だったのです。しかし時代が下るにしたがって数が減り、最後にたった1棟、東大寺の「正倉院正倉」だけが残りました。そのため今では「正倉院」と言えば、かつて東大寺の正倉院正倉だった建物を指す固有名詞となっています。
★校倉造の「正倉院」も見に行こう!
正倉院は塀の外から見学できます。せっかくお出かけするなら、正倉院展と正倉院、両方を見てコンプリートするのはいかがでしょうか。
(申し込み手続き不要、見学無料)
| 公開日 |
正倉院展の会期中は毎日 |
|---|---|
| 場所 |
東大寺大仏殿から北へ300m |
| 開館時間 |
正倉院展の会期中は10:00~16:00 |
今年絶対見ておきたい正倉院宝物セレクション
木画紫檀双六局(もくがしたんのすごろくきょく)
聖武天皇ゆかりの双六盤
北倉37、縦54.3cm、横31.0cm、高さ16.7cm
 北倉 木画紫檀双六局(全姿) 宮内庁正倉院事務所
北倉 木画紫檀双六局(全姿) 宮内庁正倉院事務所
 北倉 木画紫檀双六局(部分) 宮内庁正倉院事務所
北倉 木画紫檀双六局(部分) 宮内庁正倉院事務所
『国家珍宝帳(こっかちんぽうちょう)』に記載された聖武天皇ご愛用の双六盤。四周に立ち上がりをつけた盤面に床脚(しょうきゃく)が付く姿。木胎の上から外来のシタンの薄板を貼って作られており、表面には木画という寄木細工の技法で鳥や唐草の装飾文様が凝らされています。木画はツゲ、シタン、コクタン、象牙、鹿角、竹といった多彩な素材を用い、個々のモティーフを彩りゆたかに、かつ生き生きと表現しています。高貴な素材と高度な技術が結実した、天皇ゆかりにふさわしい品格を誇る宝物です。
花氈(かせん)
羊毛が織りなす色彩豊かな大唐花文様
北倉150、長さ272cm、幅139cm
 北倉 花氈 宮内庁正倉院事務所
北倉 花氈 宮内庁正倉院事務所
濃密な大唐花文様を全面に表した羊毛製フェルトの敷物。このような文様を表すフェルトの敷物を「花氈」といい、唐からの舶載品と考えられています。本作は藍や緑、赤などに染められた羊毛による非常に複雑な文様が精緻に表現されており、きわめて高い製作技術がうかがわれます。正倉院に伝来する37点の花氈のなかでも色彩表現が豪華で、花氈を代表する品であります。裏面には「東大寺」の墨書と「東大寺印」と読める朱印が捺され、法要の場で用いられたと考えられています。
瑠璃坏 附 受座(るりのつき うけざ)
シルクロードがもたらした東西融合の美
口径8.6cm、高さ11.2cm、重さ262.5g
 中倉 瑠璃坏 附 受座 宮内庁正倉院事務所
中倉 瑠璃坏 附 受座 宮内庁正倉院事務所
気品ある美しさをたたえた紺色のガラス器。表面に円環を貼りめぐらせた坏身を高脚が支える意匠は異国情緒にあふれ、本品がはるか西方で作られたガラス器であることを物語ります。一方、坏身の下方に取り付けられた銀製の台脚は、裾に龍のような文様が表されることから、東アジア圏において付け加えられたものとみられます。西方製のガラス器がはるばるシルクロードを経て東アジアにもたらされ、珍重されたことをうかがわせます。この種のガラス器の中でも、姿・技法ともに最高水準を示す逸品であります。
桑木阮咸(くわのきのげんかん)
琵琶も名手・阮咸の名を冠した四弦の楽器
南倉125、長さ102.0cm、胴経38.2cm
 南倉 桑木阮咸(全姿) 宮内庁正倉院事務所
南倉 桑木阮咸(全姿) 宮内庁正倉院事務所
 南倉 桑木阮咸(捍撥部分) 宮内庁正倉院事務所
南倉 桑木阮咸(捍撥部分) 宮内庁正倉院事務所
円形の胴を持つ四絃の楽器。名称は「竹林七賢」の一人で琵琶の名手とされた阮咸に由来すると言われています。中国で成立したと考えられますが、古代の遺例は本品の他に「螺鈿紫檀阮咸」(北倉30)のみ。主要部分を蘇芳で染めたクワ材で作り、細部は木画や玳瑁などで装飾しています。胴部中央の皮製の捍撥(撥受け)には、背景として八弁の大きな赤い花を、中央部に松や竹の下で高士が囲碁を楽しむ情景を描きます。胴の背面に「東大寺」の刻銘があり、東大寺の法要で用いたことがわかります。
<第77回 正倉院展>DATA
| 会期 | 令和7年(2025)10月25日(土)~11月10(月)※会期中無休 |
|---|---|
| 会場 | 奈良国立博物館 東新館西新館 |
| 開館時間 | 8:00~18:00 ※金曜日・土曜日・日曜日、祝日は20:00まで ※入館は閉館の1時間前まで |
| 観覧料金 | 観覧には事前予約制の「日時指定券」の購入が必要 一般2,000円 高校生・大学生1,500円 小学生・中学生500円 キャンパスメンバーズ券 学生400円 レイト割 一般1,500円 レイト割 高大生1,000円 レイト割 小中生無料 ・障害者手帳またはミライロID(スマートフォン向け障害者手帳アプリ)をお持ちの方(介護者1名を含む)、未就学児、レイト割(小中生)、奈良博メンバーシップカード会員の方(1回目及び2回目の観覧)、賛助会会員(奈良博、東博[シルバー会員を除く]、九博)、清風会会 員(京博)、特別支援者は無料です。 ・無料対象の方は、「日時指定券」の購入は不要です。証明 書等をご提示ください(小中学生以下は不要)。 |
| 日時指定券の発売日 | 9月5日(金)10:00~ 「日時指定券」の変更、キャンセル、払い戻し、再発行はいたしません。 |
| 販売場所・時間 |
・ローソンチケット〔Lコード:59990〕ローソンおよびミニストップ各店舗、インターネット〈https://l-tike.com/77shosoin-ten/〉 〔Cコード※入館開始時間ごと ・美術展ナビチケットアプリ |
| 日時指定券のご注意 | キャンパスメンバーズ会員の学生は、奈良国立博物館と連携する特定の大学等に属する学生のみが対象となります。当日会場入り口で学生証の提示が必要です。キャンパスメンバーズ会員校等は、奈良国立博物館ウェブサイトでご確認ください。キャンパスメンバーズの学生が誤って通常料金で「日時指定券」 を購入した場合も、払い戻し等はできませんのでご注意くださ い。 |
| レイト割について | レイト割は月~木曜日は午後4時以降、金・土・日曜日、祝日は午後5時以降の「日時指定券」に適用されます。 |
| 問合せ先 | 奈良国立博物館 TEL 050-5542-8600(ハローダイヤル) |
| 公式サイト | 〈奈良国立博物館〉https://www.narahaku.go.jp 〈正倉院展〉https://shosoin-ten.jp/ |